こんにちは!クラウドソリューション開発部の西谷です。普段生成AIを使っていて私が気を付けていることを3つにまとめて紹介します!
はじめに
生成AIは非常に便利ですが、使用方法はユーザーに委ねられており、AIの回答をどう扱うか次第で、思わぬ結果を招いてしまうことがあります。
本記事では、エンジニアである私が、生成AIを日常業務で使用していて、「あ、この使い方良くないな…」と思ったケースを交えて、自分が生成AIを使う時に気を付けているポリシーみたいなことを共有しようと思います。
前提
大前提として、私は生成AIの活用を強く推奨しています。
多くの作業においてAIは極めて強力なツールであり、積極的に使うべきだと考えています。
一方で、実際の現場では「大丈夫か、この使い方…」と感じるケースに遭遇することも少なくありません。
つまり、生成AIは非常に便利で使うべきツールですが、「適切な判断」を持って活用することが重要だという考えです。
この「適切な判断」について、実際のケースを交えて具体的に掘り下げていきます。
ポリシー1:AIは記憶装置ではない

同じ質問を何度も繰り返すのは、効率的でない使い方だと考えています。
AIへの質問と回答待ちの時間よりも、一度覚えてしまう方が圧倒的に早いからです。また、都度忘れてしまうと結果的に作業効率が下がってしまいます。
例えば「〇〇をするためのコマンドを教えて」「〇〇って何?」といった質問は、手軽にできて即座に回答が得られるため、つい記憶することを後回しにしてしまいがちです。しかし、同じ質問を繰り返している自分に気づくことがあります。
そのため「一度聞いたことは必ず覚える」を徹底し、自身のパフォーマンス向上につなげることを重視しています。
ポリシー2:判断を丸投げしない
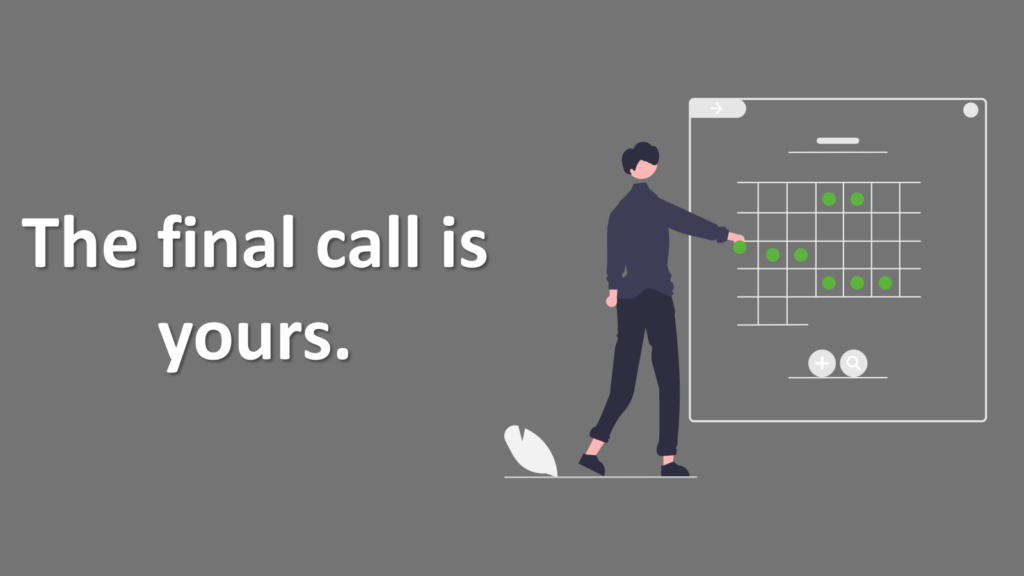
生成AIに判断や決定を丸投げするのは避けるべきだと考えています。
AIに決定を委ねると「なぜその決定に至ったか」という重要な判断根拠が失われてしまうからです。また、最終的に責任を取るのは人間であり、AIではありません。
例えば、AIが生成したコードを「動作するから」という理由だけでコードベースに統合してしまうケースがあります。この場合、なぜそのコードが書かれているかを誰も理解できず、元のコードベースとの整合性も取れません。結果として、パッチワーク的な実装が積み重なり、後のメンテナンスで大きな問題となります。
したがって「AIのサポートは受けるが、最終的な判断と責任は自分が持つ」ことを徹底すべきです。
ポリシー3:最終チェックは自分の責任
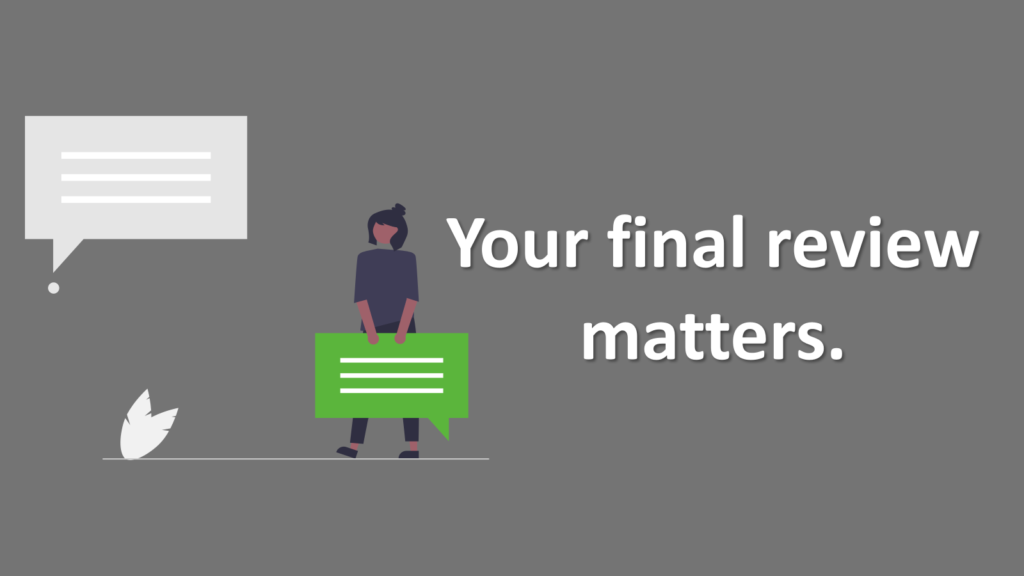
これはケース2の亜種のような感じですが、メールの返信や資料作成において、AIの出力をそのまま使用するのは危険だと考えています。
なぜなら、AIは個別の背景情報や具体的な経緯を把握していないため、実際の状況とは異なる内容を提案してしまう可能性があるからです。
仮に、クライアントからの問い合わせメールへの返信をAIに任せきりにした場合を考えてみましょう。
事前の会議で「新機能の実装は不要」と決まっていても、AIはその情報を知らないため、一般的で当たり障りのない回答を生成してしまい、実装が必要かのような内容の回答を生成してしまいます。この内容をもしも確認せず送信してしまえば、後々大きなトラブルにつながることは想像に難くありません。
そのため、「最終チェックは我々の仕事」ということを肝に銘じ、最終チェックを徹底しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
非常に便利なツールである一方、考えなしに使ってしまうと意図しない問題が起きる恐れがあります。
AIに取って代わられない人になるためにも、この記事で紹介したポリシーを大事にしたいと思っています。
最後に
エコモットでは一緒にモノづくりをしていく仲間を募集中です。弊社に少しでも興味がある方、生成AIを使った開発に興味がある方はぜひ下記の採用ページをご覧ください!





