こんにちは!
クラウドソリューション開発部の今野です。
皆さんはプレゼン行う機会ありますか?
エンジニアだと、なかなか大勢の前で話すといった機会があまりないと思いますが、プレゼンの極意を身につけることで、発表の際にグッと人を惹きつけることができます。
私は今までプレゼンをしたり、プレゼンをするための本を読み漁ったり…といったことを繰り返してきました。そのため、少しでも参考になればと思います。
ポイントは色々あるのですが、細かく書いていったら途方もないぐらいの文章量になってしまうので、今回は特に重要なポイントを押さえながら紹介させていただきます。
誰に伝えるのかを意識する

大御所のある芸人さんが言っていました。「この漫才は劇場に来てキャーキャー言っている観客に向けてやってるんやない。テレビの向こうの観客に向かって笑いを取りにいってるんや。」
プレゼンを実際に見て、感じる人は上司?同僚?顧客?
誰に伝えるのかを意識して話すことは大切ですね。
誰に伝えるのかで、話し方も変わってきます。
例えば幼稚園の子どもに自己紹介するとします。
「こんにちは、御社はIoTに関わる業務をしておりまして」
こんな伝え方しないですよね。子どもはポカーンと口を開けるか、思わず泣き出してしまいます。
ここで大事なことは、
・聞き手を取り巻く環境を意識して話す(子どもが普段どんな生活をしているのか)
・聞き手がどれくらい伝えたい内容について知っているのか
・相手に合わせた話し方・トーンを意識する(「ペーシング」といわれています)
普段の会話でも使える技になります。
「なぜ」から話す

これはサイモン・シネック氏のTEDでのスピーチ「ゴールデンサークル理論」で発表されていました。
心を動かして製品を売りたければ「Why」→「What」→「How」の順に話すべき、と。
あるプレゼンターはこのように製品を伝えます。
「こんな問題を解決するために(What)」→「こんな機能を追加しました。いかがでしょうか?」(How)
オーソドックスなセリフではありますが、顧客には話の深さが不足しているのか、イマイチ響きません。
「私たちはこのような想いをもって、日々製品を開発しています(Why)」→「そこでこんな問題を解決するべきと考えます(What)」→「そのために、このような機能が誕生しました。おひとついかがでしょうか?(How)」
説得力が増しませんか?
伝える時は、簡潔に・短く

基本的なことかもしれませんが、話すときは簡潔に・短くです。
大勢の前で話すのならなおさらです。
キーとなる言葉を考えておくことも大切ですね。今回のプレゼンでキーワードを仕込んでおいて、それをプレゼンの中で散りばめておく。
そうすると、聞いた側はプレゼン後に心に残るはず。
思いつきで話すと冗長的になってしまい、内容が散乱してしまうため避けるべきです。
3つのワードに絞って話す

この「3」という数字、プレゼンにおいては重要な数字になります。
「伝えたいことが3つあります。」
2つではなく、4つではなく、3つなんです。
スティーブ・ジョブズのiPhone発表のプレゼンでは、3つのワードを話していました。
「iPod、Phone、Internet Communicator」(これらを組み合わせた発明がiPhoneという流れの説明の中で)
この3つを何度も繰り返して話していました。3つのワードを何度も繰り返し話すことで、聞き手に印象付けています。
昔オバマ元大統領が演説で話していた「Yes, We can」もそうですね。スローガンを何度も伝えることで、印象を強めることができます。
ハキハキ話す

自分ではハキハキ話していると思いながらも、意外とハキハキしていないものです。これに気づくのに手っ取り早い方法としては、発表を動画で撮ってもらうことです。
自分のプレゼンを自分で見るのは恥ずかしいものですが、「あれ?」と気づくことがたくさんあると思います。
意外ともごもご話していた、単調で話していた、声が小さかったなど。
動画はいろんなことに気付けるのでおすすめです。
また、「ここぞ」というタイミングでジェスチャーを使うことで、強調したい部分にアクセントをつけることもできますよ。
抑揚をつける

「要は強弱つければ良いんでしょ?」と思うかもしれません。実は強弱の先を意識しなければいけないのです。
一般的に大事なポイントは、基本普通の大きさ→大事な部分は大きな声で話す
と言ったことが多いでしょう。
ですが、普通の大きさ→「あえて」小さな声で話す
といったように話すと、 聴者は「ん…?なにか大切なことなのかな?」とあえて聞き手を惹きつけることができます。でもこれは状況に応じて使い分ける必要があります。
文字を説明せず映像を話す

相手に伝える時、セリフをセリフ通りに話してしまうことがあります。
でもこれでは聴者はイメージしずらいことが多々あります。
例えば、おばあちゃんに「札幌時計台に行きたいんだけど、どうやって行くの?」と聞かれた場面に出くわしたとしましょう。
「あの角を右に曲がって、まっすぐ歩くと着きますよ。」これはこれで良いのですが、複雑な道のりなら、実際に行った時に混乱してしまいますね。
「この道をまっすぐ進むと札幌市役所が見えますね。そこを右に曲がって、まっすぐ歩くと駐車場が見えてくる。さらに進むと、記念撮影をしている観光客がたくさんいます。見上げると、そこが時計台です。」
前者と後者の何が違うのか。後者は「映像を語っているんです」。自分が実際に歩いたときに見える映像をそのまま言葉として投影しながら話しているので、わかりやすいですね。リアリティを持たせて話す。これを意識するだけで、だいぶ話の解像度が上がります。
お笑い芸人のトークは勉強になる

トークで勝負するお笑い芸人は話し上手の達人だと思っています。
昔は毎週やっていましたが、今は特別番組としてやっている「〇〇のすべらない話」がおすすめです。短時間で、聴者に情景をイメージさせて、惹きつけて最後に落とす。
セリフを全て書き出して、どこでオチを持っていっているのか確認したこともありました。
短い話の中で、疑似体験しているかのようにイメージさせ、話の構成を組み立てて話しているという点で非常に勉強になります。
実際に業務で取り入れた話
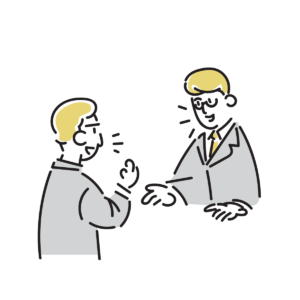
ここまで色々を挙げましたが、実際にどう活用するんだーと思うので、実際に業務で取り入れた話をします。
まずは、自身が行っている業務を社内で紹介するイベントで取り入れました。
プレゼンは淡々と話しているだけでは、聞き手を引き込むことはできません。
そのため、今回紹介させていただいた内容を活用していました。
以下、プレゼンのストーリーの流れです。
1.身近な場面を想像してもらう(聞き手がリアリティをもって場面を想像できるようにイラストやジェスチャーを用いる)←Why(なぜ)
2.問題発生!(強調する)←What(何を)
3.どうしたら良いか…(問題提起)←How(どのように)
4.今回紹介するサービスの実物を思わぬところから登場(聞き手の期待を良い意味で裏切る)
5.こんなサービスがあれば!(実際に行っている業務を紹介する)←How(どのように)
6.こういった仕組みを作る業務に関わっています。
このようにストーリーを組み立てて、プレゼンを行いました。
次に、活かせた場面としては、どのように実装するかプロジェクトメンバーに相談したい時。
「~という実装がしたい。(Why)」「~というライブラリを使ったり、~という言語で書いている。(What)」「~ということを試してみた。(How)」の順で伝えることを意識していました。(意識的にWhy、What、Howの階層を作っていくことが大事そうです)
メンバーに仕事を依頼する際も、一度に伝えずに内容を一文一文短く切ることを意識していました。
「~で、~をお願いしたくて、~が~で…」といった会話がスタートすると、聞き手はだんだん混乱してしまうため、
「~をお願いします。~というのがあります。~という流れになります。」といったように文をなるべく短く切ることが大切です。
その際にも一度に伝える内容は最大3つまでにします。(「3つのワードに絞って話す」が近い形で活かせそうです)
プレゼンや定例会の場面で「伝えることが3つあります。1つ目、~。2つ目、~。3つ目、~。」というように段落を意識して内容を伝えていました。
最後に
いかがでしょうか?
基本的なプレゼンの技について紹介させていただきました。
誰に伝えるか意識することは、日常の伝え方においても活用できると思います。
要望があれば、今後書いていきたいと思います。
弊社ではIoTに関連した、様々な案件にチャレンジすることができます。
ぜひ一緒にこれからの未来を作っていきませんか?
募集要項はこちら
最後までご覧いただき、ありがとうございました!






