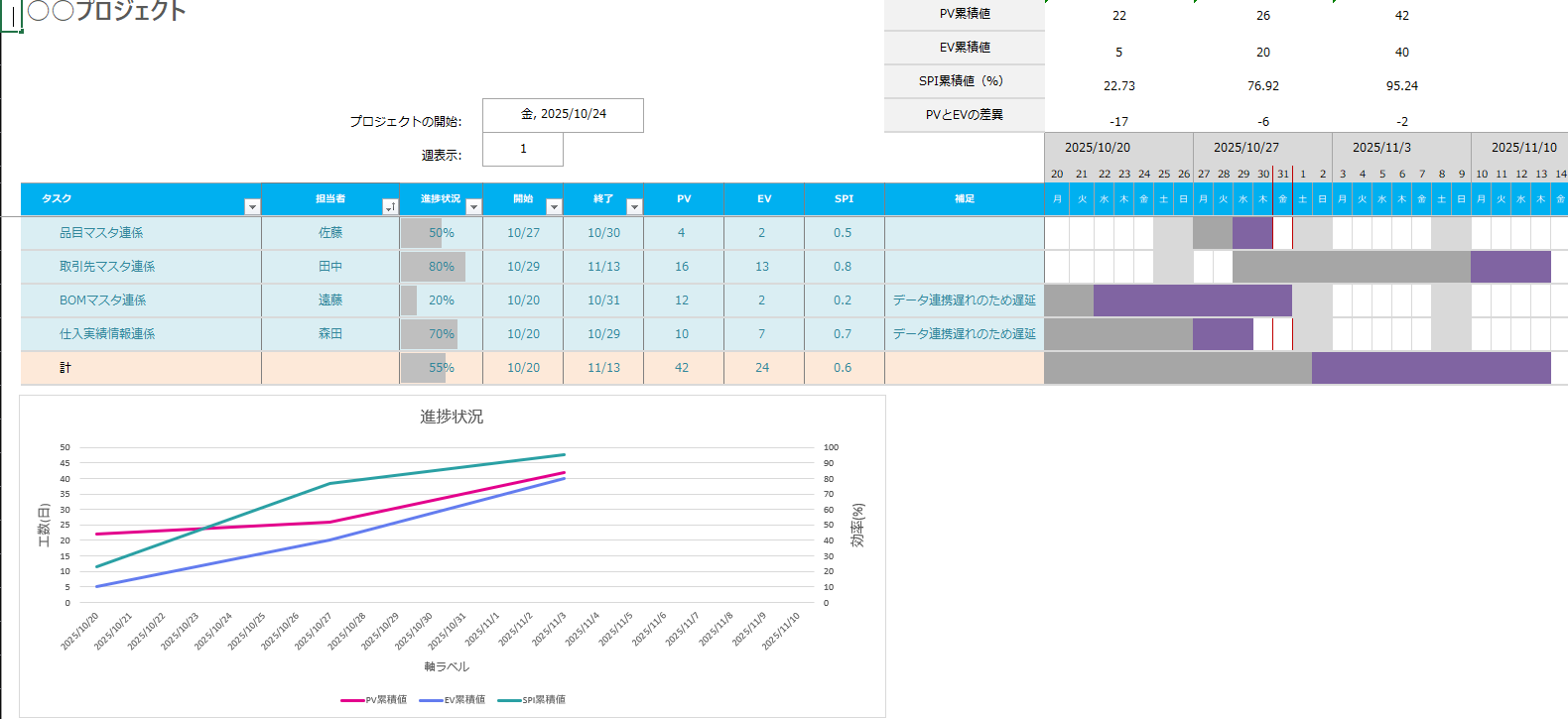お疲れ様です。SJC共同開発推進室の境田です。
プロジェクトの進捗管理、どのように行っていますか?
「今週は5工数分の遅れです」—— この報告は重要ですが、「先週と比べて、遅れは拡大しているのか? 縮小しているのか?」という傾向までは分かりません。
以前、私はPM研修で「EVM(アーンスト・バリュー・マネジメント)」という強力な進捗管理手法を学びました。
「よし、WBSにEVMを反映させよう!」と思い立って調べてみたものの、実際のWBSに組み込むための詳細なテンプレートや関数設定まで踏み込んだ記事は、意外と見つかりません。
そこで本記事では、PM研修の学びを実践に移すべく、自力で構築したEVM管理シートの作成手順を公開します。
WBS(Excel/スプレッドシート)に関数を導入し、特定の「時点」での進捗(SPIやSV)を数値化する方法から、その数値を時系列グラフで可視化し、
プロジェクトの健康状態を「点」ではなく「線」で把握する方法までをご紹介します。
出来上がったWBSは以下の通りです。
1. なぜEVMが必要か?
EVMは、プロジェクトの進捗を「工数(またはコスト)」という共通のモノサシで定量的に評価する手法です。
- PV (Planned Value): 基準日までに完了する「予定」だった作業(工数)
- EV (Earned Value): 基準日までに「実際」に完了した作業(工数)
この2つを比較することで、スケジュールの状態を客観的な数値(SPI, SV)で把握します。
SPI (スケジュール効率指数) = EV / PV
(1.0未満なら遅延)SV (スケジュール差異) = EV – PV
(マイナスなら遅延)
2. ステップ1:Excel/スプレッドシートに関数を導入する
まずはEVMの各指標を計算する仕組みをWBSに組み込みます。
WBSの構成は以下のようになっています。
E列: 計画開始日F列: 計画終了日G列: 計画工数I列: 進捗率(%) ← ※毎週手入力H列: 出来高(EV) (=G*I)

基準日と計算結果
A. EV累積値(出来高)
この値は以下の計算式の値を毎週手入力します。(進捗率が上書きされるため)
* K2セル(EV累積値):
|
1 2 |
=SUM(H7:H100) |
(※ H7:H100 は実際のタスク行範囲)
B. PV累積値(予定工数)
K1セル(PV累積値):
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
=SUMPRODUCT((E8:E11<=K5)*(G8:G11)*IFERROR(NETWORKDAYS(E8:E11,IF(K5<f8:f11,k5,f8:f11)) networkdays(e8:e11,f8:f11),if(e8:e11<="K5,1,0)))<br"> ``` ```</f8:f11,k5,f8:f11))> **C. SPI(スケジュール効率)と SV(スケジュール差異)** * `K3`セル(累積SPI%): ```excel =IFERROR(K2/K1, 0)*100 |
(※セルの表示形式を「パーセンテージ(%)」に)
* K4セル(PVとEVの差異(工数)):
|
1 2 |
=K2-K1 |
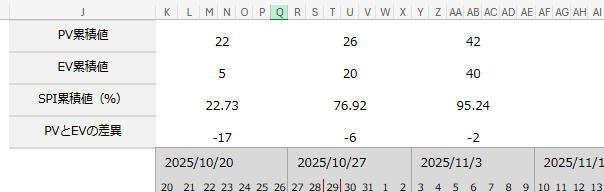
3. ステップ2:時系列グラフで「傾向」を見える化する
ステップ1で「今週のSPIは95%(-1.5工数)」といった「点」の状況が分かりました。
次に、これを「線」にするため、毎週の計算結果を別のシートに記録していきます。
A. グラフの作成
以下のようにデータを選択し、Excelやスプレッドシートの「グラフの挿入」機能を使います。
横軸
|
1 2 |
=プロジェクトのスケジュール!K5:AL5 |
フィールド1(PV累積値)
|
1 2 |
=プロジェクトのスケジュール!K1:AL1 |
フィールド2(EV累積値)
|
1 2 |
=プロジェクトのスケジュール!K2:AL2 |
フィールド3(SPI累積値)
|
1 2 |
=プロジェクトのスケジュール!K3:AL3 |
ポイントは「複合グラフ」を使うことです。
PVとEVは「工数」ですが、SPIは「%」であり、数値のスケール(縦軸の範囲)が全く異なるためです。
- グラフの種類: 複合グラフ
- 系列 1 (累積PV): 折れ線グラフ(主軸)
- 系列 2 (累積EV): 折れ線グラフ(主軸)
- 系列 3 (SPI %): 折れ線グラフ (第2軸)
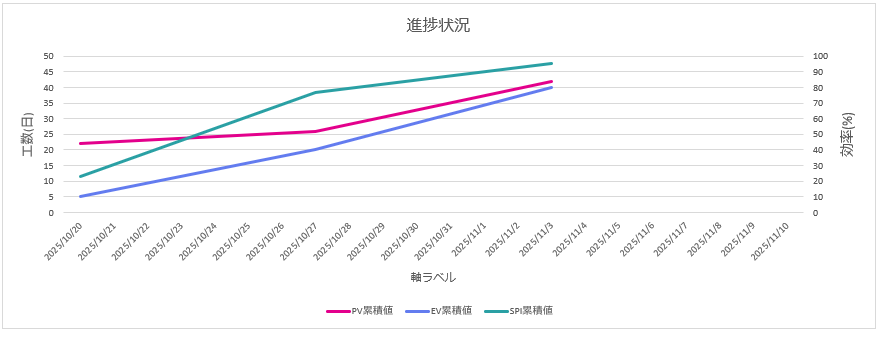
C. グラフから何を読み取るか?
このグラフが完成すると、プロジェクトの状態が一目瞭然になります。
- PVとEVの線の「差」:
- EV(実績)がPV(計画)の線を下回った瞬間、プロジェクトが遅延し始めたことが分かります。
- 2本の線のギャップ(SV)が広がっている場合、遅れが拡大傾向にある(=危険な状態)と判断できます。
- SPI(%)の線の「動き」:
- SPIが100%ライン(基準線)を下回ると、スケジュール効率が悪いことを示します。
100%ラインを回復しようと上昇傾向にあれば「リカバリー中」、下降傾向にあれば「悪化中」と判断できます。
4. まとめ:数値(点)とグラフ(線)で進捗を完全コントロール
PM研修をきっかけにEVMを導入し、最初は関数で「今」の状況を数値(点)で把握することから始めました。
さらに、その数値を毎週蓄積して「グラフ(線)」にすることで、「今」の状況が「良い傾向」なのか「悪い傾向」なのかを客観的に判断できるようになりました。
「遅れている」という事実(点)だけでなく、「遅れが拡大している」(線)という傾向まで掴めれば、PMとして「そろそろ本気で対策を打たねば」という早期の意思決定が可能になります。
最後まで閲覧ありがとうございます。
また、エコモットでは、ともに未来の常識を創る仲間を募集しています。
弊社に少しでも興味がある方はぜひ下記の採用ページをご覧ください!